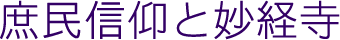鬼子母神
妙経寺は、俗に「八王子の鬼子母神」とも呼ばれています。霊験あきらかな鬼子母神の尊像を安置する寺という意味で、明治中頃からの別称です。
鬼子母神は、訶梨帝母、歓喜母、愛子母ともよばれ、もとは幼児をとらえて食べる悪鬼女でしたが、釈迦の教化によって改心し、のちには子女を庇護する善神になったといわれています。
産んだ子供の数が500とも1000ともいい、このことから安産・保育の守護神として信仰されました。

日蓮聖人は、この鬼子母神と十羅刹女(藍婆、毘藍婆、曲歯、華歯、黒歯、多髪、無厭足、持瓔珞、皐諦、奪一切衆生精気)を曼荼羅本尊に勧請して、法華経の流布する国土と信仰者を守護する神として、教義のなかに位置づけました。
妙経寺の現在地は、もと日照尼の創建した鬼子母神堂があったところで、人びとの厚い信仰が寄せられていました。「鬼子母神堂 寺町にあり 信者賽者多し」と『明治時代の八王子』に記されています。
現在の鬼子母神像は、昭和25年日甫上人によって鬼子母神堂が妙経寺に合寺され、妙経寺が再中興されたのちに安置された尊像です。
鬼子母神の像容は、天女形で右手に吉祥果をもち懐に幼児をいだく、子安鬼子母神、子育鬼子母神とよばれる尊像と、鬼神形に分けられますが、現在、妙経寺には両尊像が安置されています。
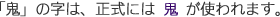
日朝堂
妙経寺が、下総国香取郡飯高村字御堂谷にあったころ、「間口三間、奥行二間」の日朝堂が建立され、日朝上人像が安置されました。
 養珠院が、三代将軍家光の養女として加賀四代藩主・前田光高に嫁いだ孫娘の、眼病平癒祈願のために建立したと伝えられるもので、その建立は寛永年中といわれています。
養珠院が、三代将軍家光の養女として加賀四代藩主・前田光高に嫁いだ孫娘の、眼病平癒祈願のために建立したと伝えられるもので、その建立は寛永年中といわれています。
日朝上人は、伊豆の宇佐美の人で行学院と号しました。俗に加賀阿闇梨ともよばれ、身延山11世、室町時代の代表的な教学者として知られています。
8歳のとき身延門流の学僧である一乗坊日出に師事して剃髪得度し、諸宗の教義を研鑽し、本覚寺日住について宗学を修めたと伝えられています。寛正3年、身延山久遠寺11世となったとき41歳であったといわれ、以来38年間にわたって貫首の座にあって活躍しました。
金洗弁財天

山門を入った左手に金洗弁財天が安置されています。
弁才天はもとは水神・農業神として尊崇されていましたが、やがて智慧の神と結んで音楽・言語の神とされ、鎌倉時代以降になって弁財天と表記され、衣食住や財宝をもたらす神となり、後に七福神にも加えられるようになりました。